この記事は「高卒で公務員になったけど後悔している」「高卒で公務員を目指すべきか迷っている」といった方に向けて書かれています。
こういった悩みを解決するために元公務員の経験を約10年持つ僕が経験談を交えながら記事を書いていきます。
この記事でわかること
・親に言われて公務員を目指している人
・世間体がいいから公務員を目指している人
・自分に向いている職種がよくわからないからとりあえず公務員と考え
ている人
この記事を見ることで公務員のリアルを知ることができます。
何も知らない状態で職種を選ぶよりきちんと知識を身につけたい方は役立つこと間違いありません。
高卒公務員のリアルな実態や後悔の理由、給料やキャリアの現実、向いている人・向いていない人の特徴まで、元公務員の視点で徹底解説します。
進路選択で後悔しないためのヒントを知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
高卒で公務員になる選択は後悔する?リアルな実態とよくある疑問

高卒で公務員になることは、安定した職業として人気がありますが、実際に働き始めてから「思っていたのと違う」と後悔する人も少なくありません。
特に、給与や昇進のスピード、学歴による待遇差、職場の人間関係など、入る前には見えにくい現実が存在します。
また、周囲の友人が大学生活を楽しんでいる姿を見て「自分も進学すればよかった」と感じる人も多いです。
この記事では、よくある疑問や後悔のポイントを具体的に解説し、あなたの進路選択の参考になる情報をお届けします。
高卒で公務員に就職した人の主な後悔ポイント
高卒で公務員になった人が後悔しやすいポイントは主に3つあります。
1つ目は「給与や昇進の差」。
大卒と比べて初任給や昇進スピードが遅く、将来的な年収や退職金にも大きな差が出ることが多いです。
2つ目は「学歴コンプレックス」。
職場で大卒の同僚と比べられたり、役職に就きにくい現実に直面することも。
3つ目は「スキルや経験の幅」。
民間企業に比べて専門的なスキルが身につきにくく、転職時に不利と感じるケースもあります。
・学歴コンプレックスを抱えやすい
・スキルや経験の幅が狭いと感じる
 ぽぴぃ
ぽぴぃよくある『できない』『生活が苦しい』の真相は?
「高卒公務員は生活できない」「給料が低くて苦しい」といった声はネット上でもよく見かけますが、実際はどうなのでしょうか。
確かに初任給や昇給ペースは大卒より遅いものの、安定した収入や福利厚生があるため、極端に生活が苦しいというケースは少数派です。
ただし、都市部や一人暮らしの場合は家賃や生活費の負担が大きく、余裕がないと感じる人もいます。
また、昇進や手当の面で大卒との差を実感しやすいのも事実です。
| 項目 | 高卒公務員 | 大卒公務員 |
|---|---|---|
| 初任給 | 約16~18万円 | 約20~22万円 |
| 昇給ペース | やや遅い | 標準 |
| 生活の余裕 | 実家暮らしなら問題なし | 一人暮らしでも余裕あり |



『高卒公務員=勝ち組』は本当か?羨ましいと言われる理由と実態
「高卒で公務員=勝ち組」と言われることもありますが、その理由は安定した雇用や福利厚生、社会的信用の高さにあります。
特に不景気の時代には、リストラの心配が少なく、ボーナスや退職金も確実に支給される点が評価されています。
一方で、昇進や給与面での限界、仕事のやりがいの少なさを感じる人も多く、必ずしも全員が満足しているわけではありません。
「勝ち組」と言われる裏側には、地道な努力や我慢も必要な現実があるのです。
・社会的信用が高い
・福利厚生が充実
・昇進や給与面での限界も



高卒公務員の給料・年収ランキングを徹底解説


高卒公務員の給料や年収は、職種や自治体によって大きく異なります。
一般的に初任給は16~18万円程度ですが、勤続年数や昇進によって徐々に増加します。
また、ボーナスや各種手当が加算されるため、年収ベースでは300万円台からスタートし、40代以降で500万円を超えるケースもあります。
ただし、大卒や民間企業と比較すると生涯年収や退職金に差が出ることが多いのが現実です。
ここでは、代表的な職種ごとの年収ランキングや、実際の給与明細例も紹介します。
| 職種 | 初任給 | 平均年収(30代) | 平均年収(50代) |
|---|---|---|---|
| 地方自治体職員 | 約17万円 | 約350万円 | 約550万円 |
| 国家一般職 | 約16.5万円 | 約340万円 | 約520万円 |
| 警察官・消防士 | 約18万円 | 約400万円 | 約600万円 |



高卒と大卒・民間企業との給料・待遇の比較
高卒公務員と大卒公務員、そして民間企業の初任給や待遇を比較すると、明確な違いが見えてきます。
大卒公務員は初任給が2~4万円ほど高く、昇進や昇給のスピードも速い傾向があります。
民間企業の場合は業界や企業規模によって大きな差があり、ボーナスや福利厚生も千差万別です。
公務員は安定性が魅力ですが、年収アップやキャリアアップを重視するなら民間企業の方が有利な場合もあります。
| 区分 | 初任給 | 昇進スピード | 福利厚生 |
|---|---|---|---|
| 高卒公務員 | 約17万円 | 遅い | 充実 |
| 大卒公務員 | 約21万円 | 標準 | 充実 |
| 民間企業(平均) | 約20万円 | 企業による | 企業による |
国家公務員・地方公務員での給与・手当の違い
国家公務員と地方公務員では、給与体系や手当の内容に違いがあります。
国家公務員は全国転勤がある分、地域手当や住居手当が手厚い傾向がありますが、基本給は地方公務員と大きく変わりません。
地方公務員は自治体ごとに給与水準が異なり、都市部ほど高い傾向があります。
また、扶養手当や通勤手当なども支給されるため、家族構成や勤務地によって実質的な年収が変動します。
・地方公務員:自治体ごとに給与水準が異なる
・手当の種類や金額は職種・勤務地で変動



高卒公務員はすごい?必要な学力や合格のための対策
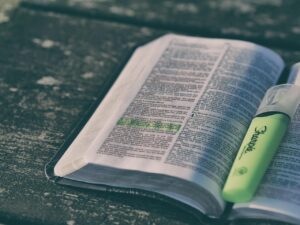
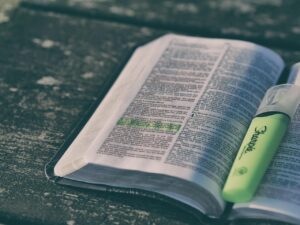
高卒で公務員試験に合格するのは決して簡単なことではありません。
学力や基礎知識だけでなく、面接や適性検査も重要視されます。
また、職種によって求められるスキルや人物像も異なるため、事前の対策が不可欠です。
ここでは、高卒公務員試験の内容や学歴要件、合格のための勉強法について詳しく解説します。
高卒で合格できる公務員試験の内容と学歴要件
高卒で受験できる公務員試験は「地方初級」「国家一般職(高卒程度)」などが代表的です。
試験内容は一般教養(国語・数学・社会・理科など)と適性検査、作文、面接が中心です。
学歴要件は「高校卒業(見込み)以上」で、年齢制限も設けられています。
倍率は年によって変動しますが、しっかりと対策すれば十分に合格可能です。
・国家一般職(高卒程度):高校卒業(見込み)以上、17歳~21歳程度
・試験科目:一般教養・適性検査・作文・面接



高卒公務員に必要なスキル・部署別の業務の違い
高卒公務員に求められるスキルは、基礎的な事務処理能力やコミュニケーション力、協調性などです。
配属先によって業務内容は大きく異なり、窓口業務や庶務、現場作業、技術職など多岐にわたります。
部署によっては体力や専門知識が必要な場合もあるため、自分の適性や希望をよく考えて受験先を選ぶことが大切です。
- 事務職:書類作成・窓口対応・電話応対
- 技術職:土木・建築・電気などの現場作業
- 現業職:清掃・施設管理・現場作業
合格者が語る勉強法と専門学校・大学進学との選択肢
高卒公務員試験の合格者は、独学や通信講座、専門学校を活用して効率的に勉強しています。
特に過去問演習や模擬試験、面接対策が重要です。
また、進学してから公務員を目指す道もあり、大学や専門学校で知識やスキルを身につけてから受験する人も増えています。
自分に合った学習スタイルや進路を選ぶことが、後悔しないためのポイントです。
- 独学:市販テキスト・過去問で対策
- 通信講座:自宅で効率的に学習
- 専門学校:短期間で集中して対策
- 大学進学:幅広い知識と人脈を得られる
将来的なキャリアと転職・独立の可能性


高卒公務員として働き始めた後、将来的なキャリアや転職、独立の可能性について不安や疑問を持つ人も多いです。
公務員は安定した職業ですが、昇進やキャリアアップの道が限られていることも事実です。
また、民間企業への転職や副業、独立を考える場合、公務員時代に培った経験やスキルがどのように活かせるのかも重要なポイントとなります。
ここでは、高卒公務員のキャリアパスや転職事情、将来性について詳しく解説します。
実際僕は真剣に仕事に取り組んだ結果、転職を選びました。全て計算し熱意を持って転職しました。そんな内容を知りたい人はこちらをどうぞ
公務員から民間に転職。独立、副業の選択肢へ。元公務員が本音を語る。
高卒公務員のキャリアパスと昇進の現実
高卒公務員は、一般職員からスタートし、係長や主任などの役職に昇進することが可能です。
しかし、大卒と比べると昇進スピードが遅く、管理職への道も狭き門となる傾向があります。
また、役職ごとに求められるスキルや経験も異なるため、日々の業務で積極的にスキルアップを図ることが重要です。
昇進を目指す場合は、自己啓発や資格取得、通信制大学での学位取得なども有効な手段となります。
- 一般職員→主任→係長→課長補佐→課長
- 大卒より昇進スピードが遅い
- 管理職への昇進は狭き門
転職しやすさ・エージェント活用や民間企業への進路
高卒公務員から民間企業への転職は、年齢や職種によって難易度が変わります。
特に若いうちは事務職や営業職などへの転職が比較的しやすいですが、年齢が上がるほど選択肢が狭まる傾向があります。
転職エージェントを活用することで、自分の強みや適性に合った求人を見つけやすくなります。
また、公務員時代に培ったコミュニケーション力や事務処理能力は、民間企業でも評価されるポイントです。
・転職エージェントの活用が有効
・公務員経験は事務・管理系職種で評価されやすい
こちらに転職エージェントのリンクを貼ります。興味ある方は僕と同じ道を歩き挑戦しましょう。
https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=45C1II+4UG10Y+5BJK+5ZEMP
大卒・専門学校卒業者とのキャリアの違い・将来性
大卒や専門学校卒業者と比べると、高卒公務員は昇進やキャリアアップの面で不利になることが多いです。
特に管理職や専門職への道は、大卒者が優遇される傾向があります。
一方で、若いうちから安定した収入を得られる点や、早期に社会経験を積める点は高卒公務員の強みです。
将来的なキャリアを考えるなら、自己啓発や資格取得、通信制大学への進学などでスキルアップを目指すことが重要です。
| 区分 | 昇進スピード | キャリアの幅 |
|---|---|---|
| 高卒公務員 | 遅い | 限定的 |
| 大卒公務員 | 速い | 幅広い |
| 専門学校卒 | 中間 | 専門職に強い |
副業や独立の可能性・公務員生活で得た経験の活かし方
公務員は原則として副業が禁止されていますが、退職後や転職後に独立する人もいます。
公務員時代に培った事務処理能力や調整力、コミュニケーション力は、民間企業や起業の場でも大いに役立ちます。
また、地域活動やNPO、コンサルタントなど、社会貢献型の仕事に転身する人も増えています。
自分の強みや経験を活かして、将来的なキャリアの幅を広げることが可能です。
・退職後の独立・起業も可能
・公務員経験は社会貢献やコンサル業で活かせる
公務員を高卒で目指すべき人・やめとくべき人の特徴


高卒で公務員を目指すべきかどうかは、個人の性格や価値観、将来の目標によって大きく異なります。
安定志向や地道な努力が得意な人には向いていますが、変化や成長を求める人には物足りなさを感じることも。
ここでは、高卒公務員に向いている人・向いていない人の特徴や、進路選択で後悔しないための自己分析のポイントを紹介します。
どんなタイプが高卒公務員に向いている?必要な適性・理由
高卒公務員に向いているのは、安定志向が強く、コツコツと地道な作業が得意な人です。
また、協調性や責任感があり、ルールや規則を守ることに抵抗がない人も適性があります。
人と接することが好きな人や、地域社会に貢献したいという思いがある人にも向いています。
一方で、変化やチャレンジを求める人にはやや物足りなさを感じるかもしれません。
・地道な作業が得意
・協調性・責任感がある
・ルールを守るのが苦にならない
・地域社会に貢献したい



高卒公務員を選ばないほうが良いケースとは?
高卒公務員を選ばないほうが良いのは、自己成長やキャリアアップを重視したい人、変化や刺激を求める人です。
また、給与や昇進に強いこだわりがある人や、専門的なスキルを身につけたい人も、民間企業や進学の方が向いている場合があります。
自分の価値観や将来像をよく考えたうえで、進路を選ぶことが大切です。
・変化や刺激を求める
・給与や昇進にこだわりがある
・専門スキルを身につけたい



進学・就職・公務員…進路を後悔しないための自己分析
進路選択で後悔しないためには、自分の価値観や将来の目標をしっかりと見つめ直すことが重要です。
「なぜ公務員を目指したいのか」「どんな働き方をしたいのか」「将来どんな自分になりたいのか」など、自己分析を深めることで、納得のいく選択ができるようになります。
家族や友人、キャリアカウンセラーに相談するのも有効です。
- 自分の価値観や目標を明確にする
- 将来像をイメージする
- 周囲の意見も参考にする
よくある質問と現役・元公務員の声Q&A


高卒公務員を目指す方や、すでに働いている方からは多くの疑問や不安の声が寄せられます。
ここでは、よくある質問とともに、現役・元公務員のリアルな体験談やアドバイスをQ&A形式で紹介します。
実際の現場の声を知ることで、進路選択や働き方のイメージがより具体的になるでしょう。
高卒公務員の求人・募集状況や傾向
高卒公務員の求人は、自治体や国家機関ごとに毎年一定数募集されています。
少子化の影響で応募者数が減少傾向にある一方、安定志向の高まりから人気は根強いです。
特に地方自治体では、地元志向の若者を積極的に採用する動きも見られます。
ただし、募集人数は年によって変動するため、最新の採用情報をこまめにチェックすることが大切です。
- 自治体・国家機関ごとに毎年募集あり
- 少子化で応募者数は減少傾向
- 地元志向の採用が増加
職員として働くメリット・不満点(待遇・手当・選択肢)
高卒公務員として働く最大のメリットは、雇用の安定と充実した福利厚生です。
有給休暇や各種手当、退職金制度などが整っており、長く安心して働ける環境が魅力です。
一方で、昇進や給与面での不満、業務のルーティン化、民間企業に比べて選択肢が少ないと感じる人もいます。
自分の価値観やライフスタイルに合うかどうかを見極めることが大切です。
- 雇用の安定・福利厚生が充実
- 有給休暇や手当が多い
- 昇進や給与面での不満も
- 業務がルーティン化しやすい
今後の景気・社会変化と高卒公務員の将来的な価値
景気や社会情勢の変化により、公務員の価値や役割も変わりつつあります。
AIやデジタル化の進展で業務内容が変化する一方、地域社会を支える仕事としての重要性は今後も高まるでしょう。
また、少子高齢化や人口減少に対応するため、柔軟な働き方や新しいスキルが求められる時代になっています。
安定性だけでなく、変化に対応できる力も今後の公務員には必要です。
- AI・デジタル化で業務内容が変化
- 地域社会を支える役割は今後も重要
- 柔軟な働き方や新スキルが求められる
まとめ|後悔しないための選択肢と行動ポイント
高卒で公務員になることには、安定や社会的信用といった大きなメリットがある一方、昇進や給与面、キャリアの幅に限界を感じる人もいます。
後悔しないためには、自分の価値観や将来像をしっかり見つめ直し、必要なら進学や転職も視野に入れる柔軟さが大切です。
情報収集や自己分析を徹底し、自分に合った進路を選ぶことで、納得のいく人生を歩むことができるでしょう。
迷ったときは、現役・元公務員の声や専門家のアドバイスも参考にしてください。
僕も公務員から転職をしている1人です。入社したからといってそこで終わりではありません。自分が望むまで道はたくさんあります。
この記事を読み、公務員になりたいと思った人は向いていると判断していいと思います。そういった人が公務員であることが国民皆が安心して住める社会になると思います。
僕の記事が気になった人はホームから転職のカテゴリーを見てください。公務員についてたくさん記事をあげています。
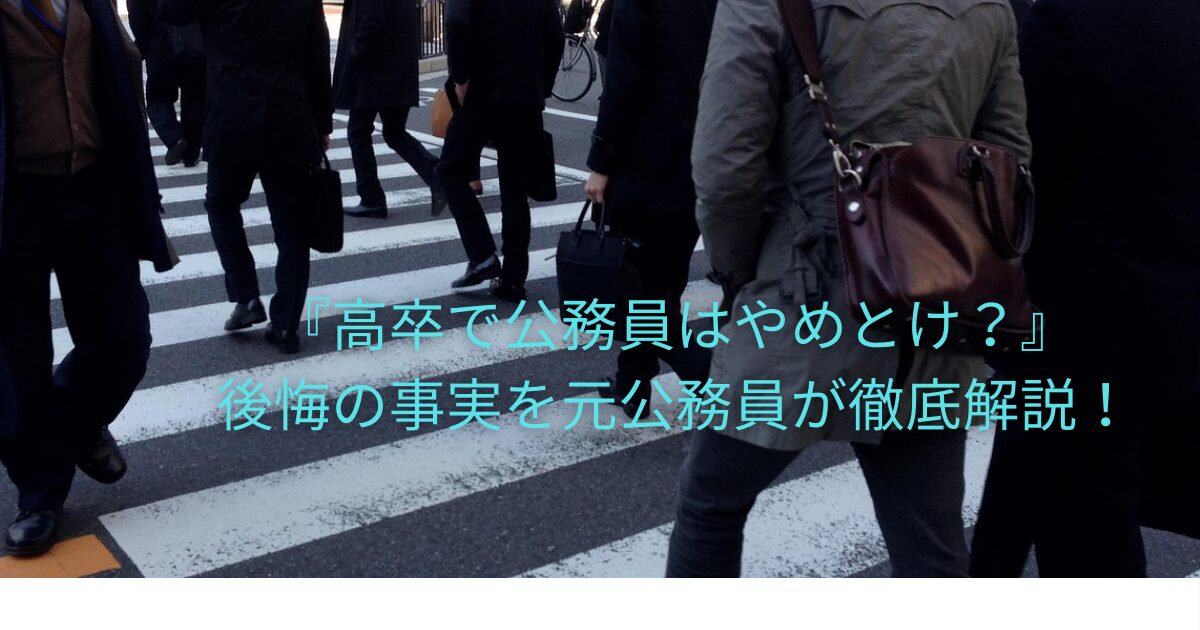

コメント