この記事は、「公務員のボーナスは多すぎるのでは?」と疑問を抱いた学生・転職希望者・現役公務員・納税者など幅広い読者に向けて、公務員ボーナスの仕組みや金額が適正かどうかをデータと現場の声で解説するものです。
僕は元公務員で現在は民間で働いています。そんな僕のリアルなボーナスの数字民間と公務員で徹底比較しています。
ネット上では感覚的な批判が先行しがちですが、本記事では法律根拠・計算式・民間との比較を交え、メリットだけでなく課題も整理します。
「もらいすぎ」か「適正」か判断するための材料を提供し、読後に自分なりの結論が出せることを目的としています。
 ぽぴぃ
ぽぴぃ公務員ボーナスの基礎知識と「もらいすぎ」議論の背景


まず、公務員ボーナスとは国家公務員法と地方公務員法に基づき支給される期末手当・勤勉手当の総称であり、企業の業績連動型賞与とは性格が異なります。
国の人事院勧告と各自治体の給与条例によって、民間平均と均衡する水準を毎年調整している点が特徴です。
それでも「税金から出るのに景気変動の影響を受けにくい」「人事評価が甘い」という批判が起こりやすく、メディアの高額支給報道が感情的な議論を助長してきました。
本章では制度の歴史と世論の温度差を整理し、論点を可視化します。
公務員ボーナスとは?期末・勤勉手当の役割と年間支給スケジュール
期末手当は企業の決算賞与に相当し、職務の特殊性や責任の重さに対する報酬として6月と12月に分けて支給されます。
一方、勤勉手当は勤務成績に応じた成果報酬的性格を持ち、査定結果で増減する仕組みです。
一般に夏季は期末手当+勤勉手当で2.1か月、冬季は2.25か月など年度によって変動します。
国家公務員の場合、人事院の勧告が秋に出て国会で承認後、12月ボーナスに反映されるタイムラグがあるため、翌年4月に差額調整が行われるケースもあります。
2025年度においては夏と冬を合わせて年間で4.65月分が支払われることになっています。
引用元 Yahoo!
https://news.yahoo.co.jp/articles/54f8f0a1befda47791e74eee5a90e49c87792a03



ボーナスもらいすぎと言われる理由:国民感情とメディア報道の実態
世論調査では「自分のボーナスがゼロ〜1か月分以下」と回答した民間労働者が約4割を占める一方、テレビ報道では平均約4.4か月分の公務員ボーナスが大きく取り上げられます。
数字だけが独り歩きして「税金で高給」という印象が強まり、民間企業の業績連動リスクとの違いが説明されにくい現状があります。
また、公務員は雇用が安定しているため不況時にボーナスが大幅減額されにくく、結果として「相対的に得をしている」と映りやすい点も批判の源泉です。
民間のボーナスは、2024年夏には一人当たり平均約41.4万円、冬には約41.3万円が支給されましたが、これはあくまで平均であり、「基本給の1~2ヶ月分」が目安とされています。
市役所や学校など仕事現場ごとの賞与事情


Sun shining on an empty Japanese classroom.
同じ公務員でも市役所・県庁・学校・消防など勤務先により手当の加算ポイントや勤勉手当係数が異なります。
例えば消防職は危険業務手当が俸給に上乗せされるため、同じ等級でも賞与額が高くなる傾向があります。
逆に学校現場の教員は時間外手当がつかない分、総年収では行政職と大差ないというデータも存在し、「先生は激務なのに安い」という声が上がる背景になっています。
- 行政職:平均支給月数4.40か月
- 技術職:平均4.45か月
- 教員:平均4.30か月(給与特別措置法により月給高め)
- 公安職:平均4.60か月(危険手当込み)



新卒採用時点での月給・賞与水準はどれくらい?
1年目夏は在籍期間が短いことから0.25か月程度、冬は1.3か月程度が目安です。
つまり1年目の年間ボーナスは約35万円前後であり、月給×4か月近い支給は2年目以降となります。
その根拠はボーナスの計算は6ヶ月分の仕事が計算されているからです。つまり、12月の賞与は6月から11月までの仕事量が比例されているからですね。
公務員ボーナスの計算方法と支給額の数字を徹底解説
ボーナス額は基本的に「俸給月額×支給月数」で算出され、扶養手当や地域手当が俸給に含まれるかは職種ごとに規定があります。
支給月数は人事院の民間給与実態調査を基に決定されるため、景気連動の遅効性が特徴です。
ここでは平均支給額だけでなく、勤勉手当の査定係数や時間外手当の取扱い等、細部を数字で確認していきます。
俸給×支給月数(か月)で決まる!基本計算式と平均支給額
例えば行政職25歳・俸給22万円の場合、2025年度の年間支給月数4.40か月をかけると約96万8,000円が理論値となります。
一方、30歳・俸給26万円なら約114万4,000円、課長補佐クラス・俸給45万円なら198万円超と、俸給テーブルに比例して上昇します。
そのため「若手は安く、管理職は高額」という格差が数字上で顕在化しやすく、SNSで話題になる高額事例の多くは管理職クラスであることが分かります。



期末手当と勤勉手当の割合を数字でチェック
2025年度国家公務員の場合、期末手当が2.55か月、勤勉手当が1.85か月で総計4.40か月と設定されています。
勤勉手当は査定により0.95〜1.15倍で上下し、5段階評価の下位10%は平均より約10万円少なくなる計算です。
つまり評価による差は存在するものの、民間の成果給ほど大きくなく「評価と連動しにくい」との批判につながっています。
| 手当区分 | 支給月数 | 特徴 |
|---|---|---|
| 期末手当 | 2.55か月 | 職務責任・職務給に比例 |
| 勤勉手当 | 1.85か月 | 勤務成績で±15%程度変動 |
年間ボーナス200万は本当?高額支給事例の内訳
課長級以上の管理職で俸給45万〜55万円、地域手当20%加算、残業80時間のケースでは、年間ボーナスが200万〜240万円となる試算があります。
しかし管理職は時間外手当が支給されないため、実質時給換算では一般職との差が縮まる場合も多く、単純に額面だけで「もらいすぎ」とは言い切れません。
公表データを見ると、200万円超の職員は全体の約5%に留まるのが実態です。
国家公務員・地方公務員・教員など職種別の支給実態と年収への影響


同じ「公務員」とひとくくりに語られがちですが、実際は職種ごとに給与表や手当構造が大きく異なります。
国家公務員は行政職俸給表(一)を中心に、専門職・公安職など複数の給与表を持ち、地方公務員は自治体ごとに条例で微調整されたテーブルを採用。
教員は「教育職俸給表」により月給が高めに設定され、代わりに時間外手当がないなど独自ルールが多いのが特徴です。
本章では、それぞれの平均賞与額と年収への寄与度を定量的に示し、「どの職種が得をしているのか」を数字で見極めます。
国家公務員のボーナス:平均支給額と給与等級
2025年度の国家公務員(行政職俸給表(一))の平均年間ボーナスは約140万2,000円で、月給に換算すると約4.4か月分です。
等級別に見ると係員(Ⅰ -Ⅰ号棒)が約85万円、係長級(Ⅱ -20号棒)が約128万円、課長補佐級(Ⅲ -38号棒)が約198万円。
上位等級ほど地域手当の20%上乗せや管理職加算が効き、額面では大きな差が出ますが、残業代がつかない管理職は手取りベースでは意外と伸びにくいという声も聞かれます。引用元 人事院
| 職層 | 平均月給 | 年間ボーナス |
|---|---|---|
| 係員 | 22万円 | 約85万円 |
| 係長 | 28万円 | 約128万円 |
| 課長補佐 | 45万円 | 約198万円 |
地方公務員(自治体職員)の支給額と地域差
地方公務員の賞与は総務省のラスパイレス指数で民間均衡を図りつつ、地域手当・寒冷地手当など自治体独自の加算で差が出ます。
東京都特別区では地域手当20%が乗るため、30歳行政職の年間ボーナスは約150万円ですが、非加算地域の県庁では同条件で約125万円に留まります。
人口10万人未満の町村では財政力指数が低く、支給月数を0.1~0.2か月削減する条例改正が行われた例もあり、地域間格差は年々広がる傾向です。
- 首都圏政令市:4.45か月+地域手当=平均150万
- 地方中核市:4.35か月で平均135万
- 町村部:4.20か月で平均120万
教員(学校現場)のボーナス:長時間勤務でも少ないって本当?
教員は教育職俸給表で月給が行政職比5~10%高めに設定される一方、時間外手当の支給がゼロ(みなし残業)である点が大きな特徴です。
文科省調査では中学校教員の月平均残業80時間超が常態化しているものの、ボーナス算定基礎には反映されません。
その結果、平均年間ボーナスは約140万円と行政職と大差なく、「労働時間あたりではむしろ少ない」という声が現場から聞こえます。



市役所・区役所職員のボーナス実態と給料テーブル
市区役所は自治体財政に直結するため、同じ政令指定都市でも黒字自治体と赤字自治体では賞与に0.05~0.1か月の差がつくケースがあります。
市民サービス部門は夜間窓口や休日出勤がある一方、時間外手当がきちんと付くため若手のボーナス基礎額が上がりやすいのが特徴です。
初任給21万円・地域手当10%の職員で、年間ボーナスは約110万~115万円がボリュームゾーンとなります。
民間企業との平均給与・賞与比較でわかる待遇良すぎ説の真偽


ここでは国税庁「民間給与実態統計調査」と厚労省「毎月勤労統計」をもとに、公務員と民間の平均賞与・年収を横並びで比較します。
結論からいえば、大企業(従業員1,000人以上)のボーナス水準に近いのが公務員であり、中小企業の平均と比べると1.5倍近い差が生じます。
この「中小との差」がネット上での『待遇良すぎ説』を生む最大の要因です。
民間企業の平均賞与・年収データと公務員を比較
| 区分 | 平均年収 | 平均賞与 |
|---|---|---|
| 公務員 | 686万円 | 142万円 |
| 民間(大企業) | 752万円 | 156万円 |
| 民間(中企業) | 504万円 | 95万円 |
| 民間(小企業) | 392万円 | 62万円 |
上表のとおり、公務員の賞与は大企業平均より約1割少ないものの、中小との格差は2倍以上に拡大しています。
そのため、大企業勤めの読者には「公務員は別に高くない」と映り、中小勤めの読者には「やはり多すぎ」と感じられる二極化が見られます。



世間体の観点からは公務員の良さは際立ちます。
しかし、現実が少々違います。なので僕は転職しました。
皆さん気になりますよね?公務員はなかなか転職できないのが現実だと多います。
気になる方は見てそんなし。
公務員から民間に転職。独立、副業の選択肢へ。元公務員が本音を語る。
待遇良すぎ?景気による変動幅を数字でチェック
リーマン・ショック時、民間大企業の賞与は前年比▲20%超減でしたが、公務員は人事院勧告で▲7%程度の微減に留まりました。
この『下げ幅の小ささ』が安定感を生み、「不況でも守られ過ぎ」と批判を呼んでいるのが実情です。
一方、景気回復局面では民間の増加幅が公務員を上回るため、長期的に見ると平均水準はほぼ収斂しています。
ボーナス支給か月数の差が生活に与える影響
4.4か月と2.0か月では年間可処分所得に約80万円の差が生じ、住宅ローン審査や教育費準備に大きく影響します。
実際、金融機関の融資基準では賞与を年収に含めて算出するため、安定した支給歴のある公務員は借入上限が民間より1~2割高く設定されやすいのです。
ボーナス廃止論や200万超え報道はなぜ起きる?制度と国民視点で検証


ネット掲示板やSNSでは定期的に『公務員ボーナスは廃止すべき』『税金で200万円は高すぎ』という声が噴出します。
しかし、法律・制度面から見るとボーナスは月給とのバランスで設計されており、単純に廃止すると基本給を大幅に引き上げる必要が生じます。
本章では議論が過熱する背景と、実際にカットを実行した自治体の事例を紹介します。
ボーナス廃止論はなぜ出るのか?制度と法律の観点
国家公務員法28条では『情勢適応の原則』に基づき、給与は民間平均に準拠すると定められています。
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120#Mp-Ch_3-Se_1-At_28
そのためボーナスのみをゼロにすると年収が民間を大幅に下回り、人材確保が困難になるという副作用が想定されます。
また、月給主体に変更すると退職手当や年金給付額が増えるため、財政負担がむしろ重くなる試算もあり、法改正議論は進んでいません。
財政難自治体でのボーナスカット例と国民の反応
夕張市や大阪府泉佐野市など財政再建団体では、支給月数を0.3~0.5か月削減した実例があります。
カット直後は住民から一定の評価を得たものの、人材流出や採用難が深刻化し、結果として行政サービス低下が問題視される事態となりました。
『カットは一時的な満足感を与えるが、長期的には地域経済にもマイナス』という教訓を残しています。



200万超え高額支給の裏側:管理職手当と評価制度
メディアで取り上げられる『課長級ボーナス230万円』の大半は、地域手当20%+管理職加算10%が上乗せされた特殊ケースです。
さらに特別昇給や単身赴任手当が俸給に含まれると、一気に金額が跳ね上がります。
しかし管理職手当は月1万~数万円と少額で、深夜残業代が付かないため、実質的な時給換算では若手職員と大差ないというデータも確認できます。
公務員ボーナスが少ないケースと評価・勤勉手当のリアル
『公務員は安定して高い』というイメージとは裏腹に、勤務成績評価が低かったり、欠勤・遅刻が多い場合は勤勉手当が大幅に減額されます。
また、人事評価B以下が3年続くと特別昇給が凍結される仕組みもあり、長期的には年収が同世代平均を下回るケースも存在します。
勤勉手当が減額される評価項目と少ないケース
勤勉手当は『目標達成度』『職務遂行能力』『勤務態度』の3軸で査定され、最低評価のD判定の場合は0.85倍に減額。
月給25万円の職員なら年間で約15万円のマイナスとなり、家計にとっては痛手です。
長時間勤務でもボーナスが伸びない理由
基本給が時間外労働の実績ではなく等級と号棒で決まるため、どれだけ残業しても俸給レンジが上がらなければ賞与基礎は増えません。
教員や管理職は残業代が付かないうえ、勤勉手当の伸び幅は±15%で頭打ちのため、『働いても報われない』と感じる要因となっています。



職員が感じる「ボーナスもらいすぎ批判」と現場の声
自治体アンケートでは『世間の批判がストレス』と回答した職員が6割を超え、特に若手ほど『実感より高額に報道される』ことへの戸惑いが強いようです。
一方で『安定しているのは確か』という自覚もあり、情報開示や働き方改革で理解を得たいという声が多数寄せられています。
また、公務員は全体の奉仕者であり束縛が強いです。
気になる方はこちら
公務員の髪型ってどこまでOK?パーマや茶髪は許される?元公務員が解説
公務員はタトゥーを入れても大丈夫?採用や懲戒処分への影響を元公務員が解説
今後の公務員ボーナスはどうなる?自治体財政と働き方改革の行方
今後のボーナス水準は、①人事院が調査する民間給与の伸び、②地方自治体の財政健全化計画、③デジタル化による業務効率化の3要因で左右されます。
2026年度以降は少子高齢化で税収が伸び悩む一方、民間の賃上げが続く見通しのため、総額は現状維持~微増がメインシナリオとされています。
人事院勧告と民間企業動向から予測する今後の支給額
2025年の春闘結果を踏まえた民間平均賃上げ率は3.4%。
過去の相関係数0.7を適用すると、公務員ボーナス支給月数は+0.05か月の増加が見込まれます。
ただし国会審議の影響で実際の支給反映は2027年度冬以降となる可能性も高く、タイムラグが続く点に注意が必要です。



地方自治体の財政健全化計画とボーナスの行方
総務省は人口減少地帯に対し、2028年度までに人件費1割削減を求める指針を示しています。
一部自治体では定年延長に伴う高コスト構造を是正するため、再任用職員の賞与を0.5か月削減する条例改正案が検討中です。
公務員志望者・現役職員が今からできる年収対策
- 副業解禁自治体を選ぶ:2024年時点で66自治体が許可制副業を導入
- 専門資格手当で俸給アップ:技術士・社会福祉士などは月5千~1万円加算
- ICTスキル研修で評価加点:DX推進プロジェクト参画は勤勉手当アップに直結
知らないと損。公務員の副業“できる?”バイトはいい?注意点を元公務員が解説
まとめ
みなさまいかがでしたかでしょうか。
話をまとめます。
正直いいかどうかは個人差があります。
・結論公務員のボーナスは高いと思います。
・基本給は低いと思います。
・残業も全てはつきません。サービス残業が8割です。
・部署にもよりますが定時で帰ることは僕は一度もありませんでしたね。
さあ皆さんこれを聞いてどう思いますか?僕は総合的に公務員いいと思いませんでいた。だから転職しました。
でも給料はさほど変化はしていません。
だからブログをやっているんです。挑戦しているんです。
この話に痺れた方はこちらもどうぞ。
知らないと損。公務員の副業“できる?”バイトはいい?注意点を元公務員が解説
そしてこれから目指している方にはこちらを

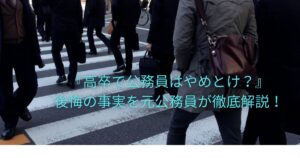
コメント