この記事は公務員として働きながら副業を検討している方、または公務員の副業ルールや最新動向を知りたい方に向けて書かれています。
僕は地方公務員約10年の経験があります。そんな経験談を踏まえ事実上の法律と相互判定し副業とはどうなのかに触れていきます。
公務員の皆さん現在の給料で十分な生活ができていますか?仕事に覆われプライベートは充実できていますか?
首を縦に触れない方は今後の生き方について少しでも変化につながるような内容となっていますのでぜひ最後までご覧ください。
今回の情報は2025年の最新情報をもとに、公務員が安心して副業を始めるための知識とリスク回避のポイントをまとめました。
副業を考える公務員の方が「何ができて、何がダメなのか」を明確に理解できる記事です。
ここで結論だけお話しします。僕の見解は公務員の方の副業はするべきではありません。ここで転職が気になる方はこちらをどうぞ
元公務員が辞めた理由と年収変化・失敗しない選択法・公務員から転職し良かったこと
内容の詳細が気になる方は下記を参考にしてください。きっと参考になるはずです。では早速見ていきましょう。
公務員の副業はできる?禁止ルールと“おかしい”と言われる理由【基本解説】
公務員の副業は原則として禁止されていますが、近年は一部で解禁の動きも見られます。
なぜ公務員の副業が厳しく制限されてきたのか、その背景や現行ルールを知ることは、副業を検討するうえで非常に重要です。
また、「副業禁止はおかしい」と感じる声や、社会の変化に伴う世論の動きも無視できません。
この章では、公務員の副業に関する基本的なルールや、禁止の理由、そして最近の解禁動向について詳しく解説します。
まず初めになぜ公務員は兼業や副業を考えるのか。僕の経験を全て伝えます。
公務員は世間から安定で高収入と思われています。
しかし、実際はそんなによくないと感じていました。
■地方公務員の平均年収は約669万円
引用元 Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/ff1931b74000c1a5d7edcf6a9bea7643006b194e
この記事で記されていることはあくまでも平均ですし、これらの金額を見ると良いと感じる人の方が多いかと思います。
実際の経験談を伝えます。
 ぽぴぃ
ぽぴぃこれらをまとめるとどこで公務員をやるかにもよりますが時間労働とと給料を考えると高いとは到底感じませんでしたね。
地方公務員、国家公務員の副業が原則禁止されてきた背景と現行ルール
公務員の副業が原則禁止されてきた背景には、公務の中立性や公正性を守る必要性があります。
公務員は国民全体の奉仕者であり、職務に専念することが求められています。
副業によって本業に支障が出たり、利益相反が生じたりすることを防ぐため、厳しいルールが設けられてきました。
現行ルールでは、営利企業への従事や自営業、報酬を伴う活動は原則禁止とされていますが、公益性の高い活動や家業の手伝いなど一部例外も存在します。
・職務専念義務の徹底
・利益相反の防止
・社会的信用の維持



2025年「最新版」地方公務員法・国家公務員法における副業禁止の規定とは
公務員の副業禁止は、地方公務員法第38条および国家公務員法第104条に明記されています。
これらの法律では、営利企業への従事や自営業、報酬を得る活動を原則禁止とし、違反した場合は懲戒処分の対象となります。
ただし、公益性の高い活動や家業の手伝いなど、任命権者の許可を得れば例外的に認められるケースもあります。
法律の条文や具体的な禁止内容を理解することが、副業を検討するうえでの第一歩です。



地方公務員法第38条 引用元総務省
https://www.soumu.go.jp/main_content/000656248.pdf
国家公務員法104条の引用元内閣官房内人事局
https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/files/kengyou_gaiyou.pdf
| 法律名 | 主な禁止内容 |
|---|---|
| 地方公務員法第38条 | 営利企業への従事・自営業の禁止 |
| 国家公務員法第104条 | 営利企業の役員兼業・自営兼業の禁止 |
“副業禁止はおかしい”と感じる理由と世論の動き
近年、「副業禁止はおかしい」と感じる公務員や一般市民が増えています。
物価高や将来不安、働き方改革の流れを受けて、副業による収入確保やスキルアップを求める声が高まっています。
また、民間企業では副業解禁が進み、社会全体で副業が一般化しつつあることも背景にあります。
こうした世論の変化を受けて、自治体や政府も副業解禁に向けた議論を進めています。
今後、公務員の副業ルールがどのように変わるのか注目されています。



副業解禁はいつから?最近の動向と自治体の事例
2020年代に入り、自治体によっては条件付きで副業を認める動きが加速しています。
特に2025年6月には、地方公務員の副業が一部解禁される新制度がスタートし、任命権者の許可を得れば副業が可能となるケースが増えています。
また、NPO活動や地域貢献活動など公益性の高い副業を推進する自治体も登場しています。
今後は、自治体ごとに副業ルールが異なる時代となりそうです。
最新の動向を把握し、自分の自治体の方針を確認することが重要です。
総務省の集計では、R6年4月1日時点で兼業の許可基準を設けている自治体は全体の64・4%にとどまる。そのうち85・2%は、営利企業との兼業を原則認めていない国家公務員の基準と同様の内容になっており、地方公務員が兼業を容易にできない要因の一つになっていますね。
引用元 読売新聞
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20250718-OYT1T50017/



公務員でも副業できる範囲と条件|地方公務員はバイトいいの?


公務員でも副業ができる範囲や条件は、法律や自治体のルールによって細かく定められています。
副業が認められるかどうかは「営利性」「公益性」「家業」「副業の規模」など複数の観点から判断されます。
また、許可が必要な場合や、申請ルールも存在します。
この章では、公務員が副業できる範囲や判断基準、許可の有無、地方公務員と国家公務員の違い、具体的なOK・NG事例について詳しく解説します。
副業できる“範囲”の考え方と判断基準(営利・公益・家業・副業)
公務員の副業が認められるかどうかは、主に「営利性」「公益性」「家業」「副業の規模」などの観点から判断されます。
営利目的の副業は原則禁止ですが、公益性の高い活動や家業の手伝い、小規模な副業は許可される場合があります。
また、収入の有無や本業への影響も重要な判断基準です。
副業を始める前に、これらの基準をしっかり確認しましょう。



・公益性:許可されやすい
・家業の手伝い:条件付きで許可
・副業の規模:小規模なら認められる場合あり
許可が必要/不要となる副業と“職場・上司”への申請ルール
公務員が副業を行う場合、許可が必要なケースと不要なケースがあります。
公益性の高い活動や家業の手伝いは、任命権者や上司の許可を得ることで認められることが多いです。
一方、資産運用や不用品販売などは許可不要の場合もありますが、収入が大きくなると申請が必要になることも。
副業を始める前には、必ず職場のルールや上司への相談・申請を行いましょう。



| 副業の種類 | 許可の要否 |
|---|---|
| 公益活動(講演・執筆など) | 許可必要 |
| 家業の手伝い | 許可必要 |
| 資産運用(株・FXなど) | 原則不要 |
| 不用品販売 | 原則不要(規模による) |
地方公務員・国家公務員で異なる副業規定と対応の違い
地方公務員と国家公務員では、副業に関する規定や対応が異なります。
地方公務員は地方公務員法、国家公務員は国家公務員法に基づき、それぞれの任命権者が許可や判断を行います。
また、自治体ごとに副業の解禁範囲や申請手続きが異なるため、同じ副業でも認められるかどうかは勤務先によって変わります。
自分がどちらの公務員かを確認し、所属先のルールを必ずチェックしましょう。
| 区分 | 主な規定 | 許可の流れ |
|---|---|---|
| 地方公務員 | 地方公務員法第38条 | 自治体ごとに異なる |
| 国家公務員 | 国家公務員法第104条 | 人事院や各省庁の判断 |
副業OK・NGになる“活動”や“収入”の具体的な線引き
副業がOKかNGかは、活動内容や収入の規模によって線引きされます。
例えば、講演や執筆など公益性の高い活動は許可されやすいですが、アルバイトや営業活動など営利目的の副業は原則NGです。
また、不用品販売や資産運用は小規模ならOKですが、継続的・大規模な収入になるとNGとなる場合があります。
副業の内容や収入が本業に影響しないかも重要なポイントです。
・アルバイト:NG
・家業の手伝い:OK(許可必要)
・不用品販売:小規模ならOK
・資産運用:OK(投資助言業などはNG)



2025最新!公務員が“できる副業一覧【合法・人気・意外なものまで】


2024年現在、公務員が合法的にできる副業にはさまざまな種類があります。
公益性の高い活動や家業の手伝い、資産運用、クリエイター系の副業など、意外と幅広い選択肢が存在します。
この章では、実際に許可されやすい副業や人気の副業、意外と知られていない副業まで、具体的な事例をリストアップして紹介します。
副業選びの参考にしてください。
執筆・講演・アンケート・モニターなど公益副業の実例
公務員が許可を得て行いやすい副業の代表例が、執筆や講演、アンケートモニターなどの公益性の高い活動です。
これらは社会貢献や知識の還元とみなされ、任命権者の許可を得れば認められるケースが多いです。
また、アンケートやモニターは短時間でできるため、本業に支障をきたしにくいのも特徴です。
・講演会・セミナー講師
・アンケートモニター
・座談会・パネルディスカッション参加
農業、家業の手伝い、小規模な不動産投資・株式投資は許可される?
農業や家業の手伝いは、家族経営の範囲であれば許可されることが多いです。
また、不動産投資や株式投資などの資産運用も、事業的規模でなければ原則として許可不要です。
ただし、農業や家業でも営利性が強い場合や、投資が本業に影響する場合は注意が必要です。
事前に職場へ相談し、必要に応じて許可を得ましょう。
| 副業の種類 | 許可の要否 | 注意点 |
|---|---|---|
| 農業・家業の手伝い | 許可必要 | 家族経営の範囲 |
| 不動産投資 | 原則不要 | 事業的規模はNG |
| 株式投資 | 不要 | 投資助言業はNG |
ユーチューバー・イラストレーター・ブログ・データ入力等のクリエイター系副業
近年では、ユーチューバーやイラストレーター、ブログ運営、データ入力などのクリエイター系副業も注目されています。
これらは自宅でできるため、本業に支障をきたしにくい一方、収益が大きくなった場合や広告収入が継続的に発生する場合は、営利活動とみなされる可能性があります。
副業の規模や内容によっては許可が必要となるため、事前に職場へ相談し、ルールを守ることが大切です。
また、顔出しや実名での活動は公務員としての信用失墜リスクもあるため、慎重に判断しましょう。
- ユーチューバー(動画投稿・広告収入)
- イラストレーター(作品販売・受注制作)
- ブログ運営(アフィリエイト・広告収入)
- データ入力・クラウドワークス系業務
資産運用(FX・仮想通貨など)や本業との兼業パターン
資産運用(FX・仮想通貨・株式投資など)は、原則として副業に該当せず、許可不要で行うことができます。
ただし、投資助言業や他人の資産運用を業として行う場合は営利活動となり、禁止されます。
また、資産運用による収入が本業に影響を与えるほど大きくなった場合や、取引が事業的規模に達した場合は注意が必要です。
本業との兼業パターンでは、職務専念義務や信用失墜行為に該当しないよう、慎重に行動しましょう。
・FX・仮想通貨取引
・不動産投資(小規模)
・投資助言業はNG



不用品販売など“小さな収益”はどこまで認められる?
フリマアプリやネットオークションでの不用品販売は、家庭内の不要品を処分する範囲であれば副業に該当せず、許可不要です。
しかし、継続的に仕入れ・販売を行い、事業的規模になると営利活動とみなされ、禁止される場合があります。
収益が大きくなった場合や、販売が本業に影響する場合は注意が必要です。
副業とみなされるかどうかの線引きは、収入の規模や継続性がポイントとなります。
| 活動内容 | 副業該当性 | 許可の要否 |
|---|---|---|
| 家庭の不用品販売 | 該当しない | 不要 |
| 仕入れ販売(継続的) | 副業に該当 | 必要 |
“ダメ・禁止”になる副業とは?失敗事例・懲戒処分になる理由と原因


公務員が行ってはいけない副業には明確な基準があります。
営利目的のアルバイトや営業活動、事業的規模の副業は原則禁止です。
また、本業に支障をきたす副業や、公務員としての信用を損なう行為もNGとなります。
この章では、禁止される副業の具体例や、実際に懲戒処分となった失敗事例、バレる原因について詳しく解説します。
報酬・利益が発生する副業のNGラインと“営利目的”の解説
公務員が報酬や利益を得ることを目的とした副業は、原則として禁止されています。
特に、アルバイトや自営業、営業活動などは営利目的とみなされ、法律違反となる可能性が高いです。
一方で、公益性の高い活動や家業の手伝いなどは、営利性が低い場合に限り許可されることがあります。
副業の内容や収入の規模によって、NGラインが変わるため注意が必要です。
・自営業(ネットショップ運営等):NG
・営業活動(保険・不動産等):NG
・公益活動・家業の手伝い:条件付きでOK
職務専念・公益性・信用失墜(副業が本業に影響するケース)
副業が本業に悪影響を及ぼす場合や、公務員としての信用を損なう行為は厳しく禁止されています。
例えば、深夜まで副業をして本業に支障が出たり、公務員の立場を利用した営業活動を行ったりすることは、職務専念義務違反や信用失墜行為に該当します。
また、SNSやネット上での発信が問題となるケースも増えているため、情報発信には十分注意しましょう。
- 本業に支障をきたす副業
- 公務員の立場を利用した営業
- 信用失墜行為(不適切な発信など)
副業バレた事例:懲戒処分・停職・減給の背景と主な原因
副業がバレて懲戒処分となった事例は少なくありません。
主な原因は、住民税や確定申告での収入発覚、SNSでの副業アピール、同僚や知人からの通報などです。
懲戒処分には停職や減給、最悪の場合は免職となるケースもあります。
副業を行う際は、必ずルールを守り、リスクを十分に理解しておくことが重要です。
コンビニでアルバイトをしていた方が170万円の副収入を得ており懲戒処分になった記事です。
引用元 NHK
https://www3.nhk.or.jp/lnews/okayama/20250722/4020023983.html
県立病院で働く23歳女性無許可で副業300万円の収入
停職1ヶ月の懲戒処分
引用元Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/1c966de7f4fa790ea95f9c1d8b802d71cdd3886a
| 処分内容 | 主な原因 |
|---|---|
| 停職・減給 | 無許可のアルバイト・営業活動 |
| 免職 | 継続的な副業・虚偽申告 |
副業禁止なのになぜバレる?公務員が陥りやすいポイントと対策
副業がバレる主な理由は、住民税や確定申告での収入申告、SNSやネットでの情報発信、同僚や知人からの通報です。
特に、住民税の特別徴収や副業収入の申告漏れは発覚しやすいポイントです。
バレないためには、収入の管理や情報発信の方法、職場のルール遵守が不可欠です。
また、許可が必要な副業は必ず申請し、リスクを最小限に抑えましょう。
・SNS・ネットでの情報拡散
・同僚・知人からの通報
・申請漏れ・虚偽申告



【副業のやり方】公務員がバレない方法・注意点・事前確認のポイント


公務員が副業を行う際には、バレないための工夫や注意点、事前に確認すべきポイントがいくつかあります。
特に、住民税や確定申告の処理方法、職場への申請や許可の取得、情報発信の仕方などが重要です。
また、ルール違反を避けるためにも、最新の法令や自治体ごとの規定をしっかり把握しておく必要があります。
この章では、公務員が副業を始める前に知っておきたい実務的なアドバイスや、バレないためのポイントを解説します。
バレるバレないを考える前にこの記事を読んでいるあなたは公務員としてではなく新たな道を探そうとしていることに気づいてください。
公務員である以上副業はリスクを伴います。
今この言葉に少し不安を感じた方は転職を視野に入れた方が絶対にメリットがあります。無料登録できますのでまず登録をすると道が開けます。実際僕もそこからはじましました。まずは知ることから始めましょう。
【転職エージェントナビ】
![]()
![]()
住民税・確定申告・収入申告で副業が発覚しやすいケース
副業がバレる最大の原因は、住民税や確定申告での収入申告です。
副業収入がある場合、住民税の納付方法によっては職場に通知が届き、発覚することがあります。
また、確定申告時に「特別徴収」を選ぶと職場に副業収入が伝わるため、「普通徴収」を選択するのが一般的な対策です。
ただし、申告漏れや虚偽申告は重大なリスクとなるため、正しい手続きを心がけましょう。
- 住民税の納付方法(特別徴収・普通徴収)
- 確定申告時の申告内容
- 収入申告の有無
- 申告漏れ・虚偽申告のリスク



副業する前に必要な許可・手続き・上司相談の実務的アドバイス
副業を始める前には、必ず職場の規定を確認し、必要に応じて上司や人事担当者に相談しましょう。
公益性の高い活動や家業の手伝いなどは、任命権者の許可が必要な場合が多いです。
許可申請の際は、副業の内容や収入、勤務時間への影響などを具体的に説明することがポイントです。
また、許可が下りた場合でも、定期的に状況報告を求められることがあるため、誠実な対応を心がけましょう。
・上司・人事への相談
・許可申請書の提出
・副業内容・収入・影響の説明
副業活動を“バレない”ための注意点と守るべきルール
副業がバレないようにするためには、情報発信や収入管理に細心の注意を払う必要があります。
特にSNSやブログでの実名・顔出し活動はリスクが高いため、匿名での活動や個人情報の管理を徹底しましょう。
また、収入が増えた場合は必ず正しく申告し、職場のルールや法令を遵守することが大切です。
バレないことだけを目的にせず、リスクを理解したうえで健全な副業を心がけましょう。
・個人情報の管理徹底
・収入の正確な申告
・職場・法令のルール遵守
【Q&A】公務員の副業に関するよくある質問・最新動向まとめ
公務員の副業に関しては、制度の変化や自治体ごとの違い、税金の取り扱いなど、さまざまな疑問や不安が寄せられます。
ここでは、よくある質問とその回答、最新の動向や注意点についてまとめました。
副業を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
副業解禁の今後の動きは?自治体ごとの違いと最新情報
2025年以降、地方公務員の副業解禁が進み、自治体ごとに副業ルールが異なる時代となっています。
一部自治体では、公益活動や地域貢献型副業を積極的に認める動きが加速しています。
今後も副業解禁の流れは続くと予想されますが、詳細なルールや許可基準は自治体ごとに異なるため、最新情報を常にチェックしましょう。
| 自治体 | 副業解禁の内容 |
|---|---|
| 東京都 | 公益活動・地域貢献型副業を許可 |
| 大阪府 | 家業の手伝い・農業など一部副業を許可 |
| 福岡市 | NPO活動・講演活動などを許可 |
副業で得た収入の申告・税金の取り扱い(確定申告・住民税)
副業で得た収入は、原則として確定申告が必要です。
住民税の納付方法によっては職場に副業がバレるリスクがあるため、確定申告時には「普通徴収」を選択するのが一般的です。
また、収入が20万円を超える場合は必ず申告が必要となります。
税金の取り扱いを誤ると、後々大きなトラブルにつながるため、正しい知識を持って対応しましょう。
・住民税は「普通徴収」を選択
・20万円以上の収入は必ず申告
・税金の知識を身につける
副業に関するよくある悩み・疑問と元公務員の解説
副業を始めたいが、どこまでがOKなのか分からない、バレたらどうなるのか不安、どんな副業が人気なのか知りたい――こうした悩みは多くの公務員が抱えています。
元公務員の立場から言えるのは、まずは職場のルールを確認し、許可が必要な場合は必ず申請することが大切です。
また、無理のない範囲で副業を行い、リスクを最小限に抑えることが賢明です。
不安な場合は、専門家や経験者に相談するのもおすすめです。
・許可申請を怠らない
・無理のない範囲で副業
・専門家への相談も有効
まとめ|公務員副業時代の“賢い選択”とリスク回避のポイント
公務員の副業は、法律や自治体ごとのルールを守れば、安心して行うことができます。
副業解禁の流れが進む中で、賢くリスクを回避しながら、自分に合った副業を選ぶことが大切です。
本業に支障をきたさず、社会的信用を損なわない範囲で副業を楽しみましょう。
最新情報を常にチェックし、必要な手続きや申告を怠らないことが、公務員副業時代の賢い選択です。
民間に転職した僕の考えたですが、副業を考えるような方は転職しましょう。また独立するような知識を得たほうが隠れてするより利益は倍増するでしょう。
僕は実際副業の選択を考えて転職しました。実際こうしてブログも行っています。転職に少しでも興味がある方はこちらをご覧ください
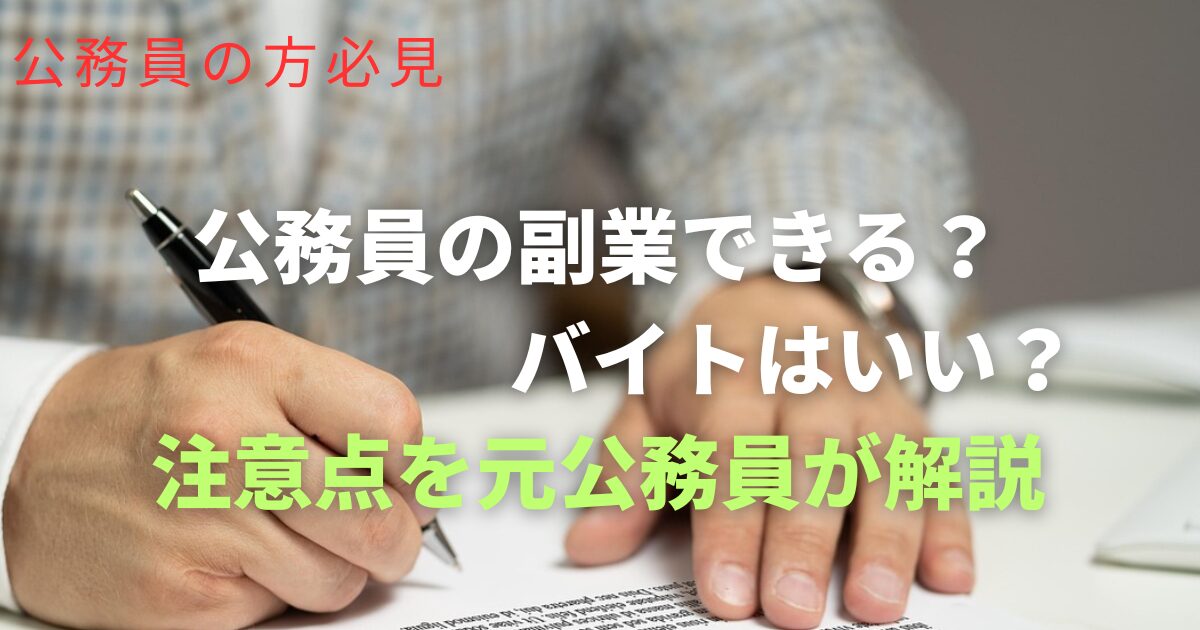




コメント